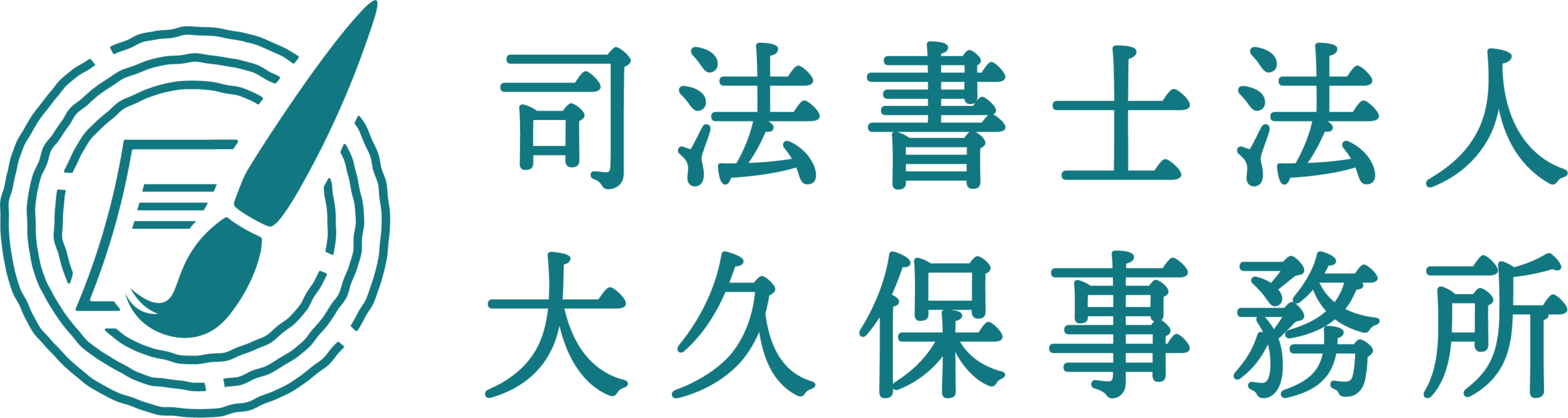家族信託
(『終活まるごとパッケージ』オプション)
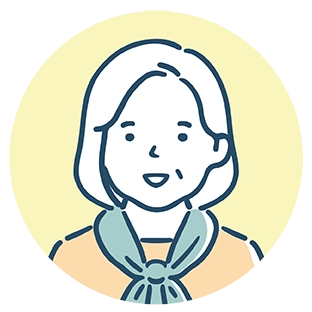
ひとことで言うと、どういうメニューですか?
どんな人におすすめですか?

お任せできるご家族がいて、かつ、特定の財産に関する処分や管理をお任せしたい場合に使う仕組みです。
(ご家族がいない場合や、財産を特定せずに委任したい場合は、財産管理契約や任意後見を使います)
家族信託とは
家族信託とは、「財産の管理や運用を家族に託す仕組み」のことです。
特に高齢者が自分の財産を安心して管理し、将来に備えるために使われる方法として注目されています。
難しいイメージがあるかもしれませんが、簡単に言えば「信頼できる家族に財産の管理をお願いする仕組み」です。
家族信託は、高齢者が将来の財産管理や相続対策のために使える便利な制度です。
親が元気なうちに、家族でしっかり話し合い、専門家の力を借りて進めることが大切です。
認知症や相続トラブルの不安を減らし、家族全員が安心できる方法として活用を検討してみましょう。
家族信託が必要な理由
特に認知症などで意思決定が難しくなった場合、自分の財産を自由に使えなくなることがあります。
認知症などで判断能力が低下すると、銀行口座が凍結され、不動産の売却もできなくなることがあります。
家族信託をしておけば、判断できなくなった後も、家族が代わりに財産を管理・活用できます。
法定後見とは異なり、任意後見同様、自分が元気なうちに家族と柔軟にルールを決められるのが特徴です。
たとえば、高齢の親が「もし認知症になったら、自分の代わりに息子に財産を管理してほしい」と考えた場合に家族信託を使います。
家庭裁判所による管理外なので、比較的自由に設計ができます。
反面、お任せできるご家族がいない場合や、財産を特定せずにお任せしたい場合には向きません。
(その場合は財産管理契約や任意後見を使います)
家族信託の登場人物
家族信託には、次の3つの役割があります。
家族信託のメリット
認知症対策ができる
親が判断力を失っても、家族が財産を管理できる。
財産の使い道を
自由に決められる
親が元気なうちに、「このお金は介護費用に」「家は特定の子どもに相続させる」といった細かいルールを設定できる。
柔軟な財産管理が可能
成年後見制度(法定後見・任意後見)よりも柔軟で、親の希望をより反映しやすい。
相続トラブルを防げる
あらかじめ財産の分配ルールを決めておくことで、相続の際の家族間の揉め事を防げる。
家族信託の注意点
法律や手続きが複雑
信託契約書を作成するためには、専門家(司法書士など)のサポートが必要。
費用がかかる
契約書の作成や不動産の名義変更には費用が発生します。
信託された財産は
受託者が管理
受託者がしっかり管理しないとトラブルになる可能性があります。
信頼できる人を選ぶことが重要です。
契約で特定した
財産以外は信託の範囲外
契約で特定した財産以外は信託の範囲外です。
また年金や生命保険など、信託の対象にならない財産もあります。
家族信託の具体例
ケース1
認知症対策
高齢の親が「もし認知症になったら、自分の預金を介護費用や生活費として使ってほしい」と考え、長男に信託します。
親が認知症になっても、長男が親のために必要なお金を管理・支出できます。
ケース2
相続対策
親が「自分の財産を子どもたちに平等に分けたいが、家は長男に残したい」と希望した場合、家族信託でそのルールを決めておけば、相続時のトラブルを防げます。
※遺言と違い、契約なので、両者の合意が必要です
ケース3
不動産の管理
親が持つアパート経営を子どもに任せたい場合、家族信託で管理を託すことができます。
親が亡くなった後も、そのアパート収益を家族に分配するルールを設定できます。
ケース4
不動産の売買
親が長期の入院等、直接売買ができない場合、家族信託で家族が契約当事者として売買ができるようになります。
売却した代金は家族のものにはならず、所有していた親の財産になります。