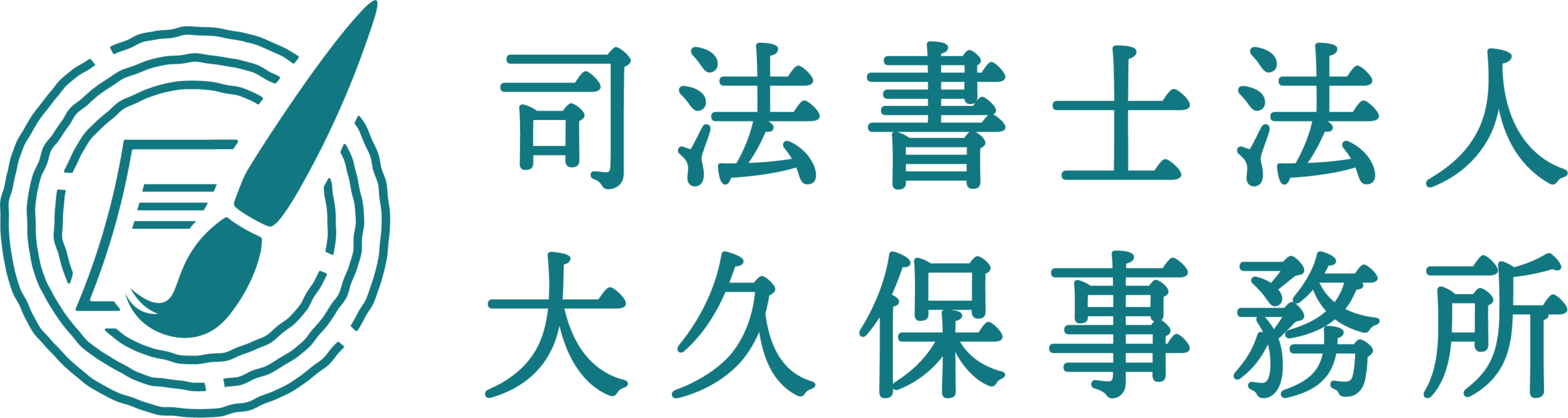任意後見
(終活まるごとパッケージ)

ひとことで言うと、どういうメニューですか?
どんな人におすすめですか?

「財産管理委任契約」では、ご本人の判断能力がなくなった場合、様々な手続きが代行できなくなります。
それに備える制度です。
判断能力があるうちにご契約の必要がありますが、判断能力がある間は、月額費用は発生しません。
判断能力がなくなったときに、「財産管理委任契約」から「任意後見」に移行します。
裁判所が選任する法定後見制度と違い、判断能力があるうちに、誰に後見人になってもらうかをあらかじめ決めておくことができます。
任意後見契約は「終活まるごとパッケージ」に含まれるメニューです。
任意後見契約のみをご希望の場合は別途お問合せください。
任意後見とは
任意後見制度は、「成年後見制度」のうちのひとつです。
将来、ご本人が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。
「成年後見制度」には、以下の2種類があります。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
成年後見制度
判断能力が不十分になったときに家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度では、
見知らぬ専門家(司法書士や弁護士など)が選任されることも多いです。
任意後見では頼れる人を選んでおけるので安心感が違います。
私たちなら以下のような
サポートができます
人生の大切な節目や予期せぬ出来事に備えて、任意後見人を選任することは、ご自身の未来を守るための重要なステップです。
私たちは、豊富な経験と確かな実績を持つ専門家として、任意後見人の役割を誠実に、そして責任を持って引き受けます。
私たちが提供するサービスの特徴は、以下の通りです。
経験豊富な専門家が
サポート
私たちは、法的な知識と実務経験を活かし、任意後見人としての業務を確実に遂行します。
財産管理から生活支援に至るまで、幅広い対応が可能です。
安全性と信頼を最優先
あなたの財産や生活を守るために、私たちは透明性の高い管理、適切な対応を心がけています。
すべての手続きが、法的に正当かつ透明であり、不正行為の防止にも万全の体制を整えています。
本人の意思を尊重した
サポート
任意後見制度の本来の目的は、本人の意思を尊重することです。私たちは、その意向を最優先に考え、必要な支援を行います。
ご自身の意見や希望を反映した生活ができるよう、最適な方法でサポートします。
私たちは、任意後見人として、信頼できるパートナーであることをお約束します。
財産の管理や生活のサポートに不安を感じている方々に対し、安心感と信頼を提供し、あなたの大切な未来をしっかりと支えます。
今すぐご相談ください。私たちが、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。
具体的な事務委任を見る
任意後見の具体的な支援の内容は以下の通りです。
第1 継続的管理業務
- 甲に帰属する全ての財産及び本契約締結後に甲に帰属する財産並びにその果実の管理・保存に関する事項
- 金融機関、郵便局、証券会社、保険会社との全ての取引に関する事項
- 定期的な収入の受領及び定期的な支出を要する費用の支払い並びにこれらに関する諸手続に関する事項
- 生活費の送金や日用品の購入、その他日常生活に関する取引に関する事項
- 日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入に関する事項
- 保険金の受領に関する事項
- ①登記済権利証、②実印・銀行印、③印鑑登録カード、④個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、⑤預貯金通帳、⑥年金関係書類、⑦各種キャッシュカード、⑧有価証券・その預り証、⑨健康保険証、介護保険証、⑩建物賃貸借契約書等の重要な契約書類・証書等の保管及び事務処理に必要な範囲内での使用に関する事項
- 行政機関の発行する証明書の請求に関する事項
- 介護、福祉サービスの利用契約の締結、変更、解除及び費用の支払いに関する事項
- 復代理人及び事務代行者の選任に関する事項
- 以上の各事項の処理に必要な費用の支払いに関る事項
- 以上の各事項に関連する一切の事項
第2 個別的管理業務
- 甲に帰属する全ての財産及び本契約締結後に甲に帰属する財産並びにその果実についての処分、変更に関する事項
- 不動産の売却、賃貸不動産の管理、賃貸借契約の締結、変更、解除に関する事項
- 金銭消費貸借契約、担保権設定契約の締結、変更、解除に関する事項
- 相続に伴う遺産分割や相続の承認・放棄、贈与又は遺贈の拒絶・受諾、寄与分を定める申立て、遺留分侵害額の請求に関する事項
- 登記・供託に関する申請に関する事項
- 税金の申告、納付に関する事項
- 要介護・要支援認定の申請並びに認定に関する承認又は審査請求の申立てに関する事項
- 福祉関係施設への入所に関する契約の締結、変更、解除及び費用の支払いに関する事項
- 福祉関係の措置の申請及び決定に関する審査請求の申立てに関する事項
- 居住用不動産の購入に関する事項
- 借地契約及び借家契約の締結、変更、解除に関する事項
- 住居等の増改築、修繕に関する請負契約の締結、変更、解除に関する事項
- 医療契約の締結、変更、解除及び費用の支払いに関する事項
- 病院への入院に関する契約の締結、変更、解除及び費用の支払いに関する事項
- 行政機関等に対する諸手続に関する事項
- 上記業務以外の、甲の生活、療養看護及び財産管理(財産処分を含む)に関する一切の法律行為に関する事項
- 上記「第1 継続的管理業務」、「第2 個別的管理業務」の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する下記行為に関する事項
- 裁判外の和解、示談並びに仲裁契約
- 行政機関等に対する不服申し立て及びその手続の追行
- 司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に定める手続の追行
- 弁護士に対して訴訟行為や民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項についての授権
- 復代理人及び事務代行者の選任
- 以上の各事項の処理に必要な費用の支払い
- 以上の各事項に関連する一切の事項